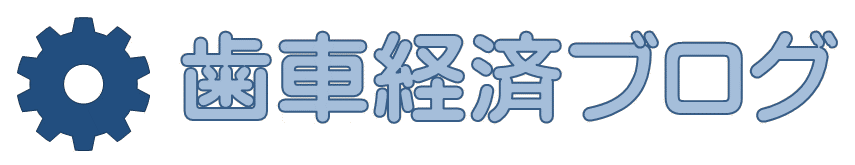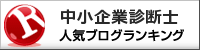人気ブログランキングに参加しています。
↓↓↓ まずはクリックお願いします。
今回は経済学の話。元々はSEだったものの、当時はデフレで景気が悪く、就職もままならない状態。理系・大学院卒でも就職は厳しかったです。プログラミングなどもできたものの、当時は自分よりスキルの高い人もいて、そんな人すら安く買い叩かれる時代でした。
SE1本でやっていくのは厳しいと感じ、経営や経済に関するスキルを身に着け将来を見据えていました。そういうこともあり、中小企業診断士を志すという流れになりました。当時は学んだ経済学のスキルを使い、世の中の流れをいろいろと見ていました。
当時に憧れていたのが三橋貴明氏。中小企業診断士で経済評論家という立ち位置の方でした。2010年代当時は診断士試験に数回落ちていたこともあり、やはり憧れの存在だったというのはあります。まあ、2012年以降は私と経済に対する考え方が異なってきたということもあり、そのころからブログの方もほとんど見なくなりました。
2012年までは民主党政権でしたが、日本経済は1990年代から続くデフレに悩まされてきたというのがあります。アベノミクスはそのデフレ脱却を目指すというもので、金融政策と財政政策を組み合わせるというもの。閉鎖経済であればIS-LM曲線でそれぞれ表され、開放経済であればマンデルフレミングモデルで説明できる政策です。
2012年当時や、そこからまだしばらくの間、経済政策としてはデフレ脱却策を打つ必要がありました。「何言ってんの?デフレでしょ。」が通用した時代です。昨今、ネットを見ていると、未だにデフレのまま思考が止まっているのでは?というような方も見受けられます。
一応デフレって、一般的な定義では物価が継続的に下落する現象です。確かに2010年代前半まではその傾向が続いていました。またコロナの一部時期もそんな感じです。ところがコロナを終えると、これまでコロナでモノの行き来が制限されていたのが、痺れを切らしたかの如く、一気に物流やサービスが流れた感じでした。
その結果、物価は上昇。最近聞く話は、「モノの値段の上がり具合が激しい。」「やれ電気代。ガソリン代。果てはコメまで高くなっている」と。物価は、トータルの製品・サービスの価格上昇の加重平均になるので、特定のモノの値段というわけではありませんが。
そういえば、2016年あたりで当時の安倍首相が「もはやデフレではない」と言っていたかと思います。黒田バズーカの影響もあってか、日本経済の状況も変わってきました。特に最近は賃上げの動きも少しずつ出ています。本格的に動くのはもう少し先になりそうですが。
~人気ブログランキングに参加しています~
良ければ応援クリックお願いします。