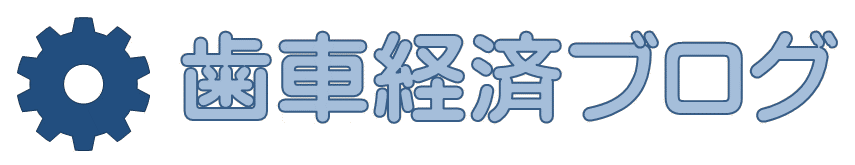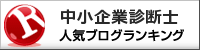人気ブログランキングに参加しています。
↓↓↓ まずはクリックお願いします。
政治経済関連のブログを過去に書いていて、最近もいくつかブログ等を巡回し、Xなどでも情報収集しています。SNSの場合は自分と似たような意見が集まりやすいですが。
昨今問題になっているのが物価高対策。まあこれはインフレですから仕方がありません。2012年の頃はまごうことなきデフレでしたから、「デフレ脱却策」を打つ必要があります。そういう意味では、当時の野田政権が社会保障と税の一体改革を推し進めましたが、時期としては失敗でした。
消費税増税は基本はインフレ時に行いたい政策になります。デフレの時に消費税を増税すると、デフレをさらに悪化させます。この時点ではまずはデフレ脱却策。その後はアベノミクスの第1の矢と第2の矢にあった政策が必要でした。
特に当時は黒田バズーカの影響もあり、デフレは早々に終わりました。デフレの定義は物価の継続的な下落ですから、この時点ではいったん歯止めがかかった状況でした。
とはいえ、「デフレが終わっただけ」で、インフレには届いておらず、宙ぶらりんな状態がしばらくは続いていましたから、やはり「デフレ脱却策とほぼ同じような政策がもうしばらく必要」な状態でした。
金融政策は実行されたものの、途中でデフレ脱却中に消費税を2回増税したものですから、景気の回復スピードは緩やかになります。このため、2010年代は序盤でデフレを脱却したものの、そこから経済回復のスピードは遅かったといえます。
また、長い間デフレが続いていたので、人々の間で「デフレマインド」が進行していました。デフレは物価の経済的下落であり、貨幣価値は(人々が知っているか知らないかは別として)上昇傾向になります。モノやサービスの価格が下がるということは、モノやサービスの価値は相対的に下がり、お金の価値が上がります。
ということで、貨幣価値が上がるので、多くの人が「貯金する」という行動に流れます。つまりはお金の動きが悪くなり、景気の停滞状況が続くということになります。「人々のマインドの修正」はどうしても時間がかかりますから、景気回復策は時間がかからざるを得ないということになります。
あとは「工場はテレポーテーションできない」というのもあります。民主党政権時はお金の量が足りず、お金の価値が高い。しかるに「円高」になりやすいわけです。円高だと「海外で作った方がお得」となり、中小企業さえも海外に工場を作るという時代でした。所謂国内空洞化。これが国内景気を冷え込ます追加要因になります。
黒田バズーカ後に、一部の工場が国内回帰を果たすという状況に変わりました。そうなると、国内に雇用が生まれ始めるので、アベノミクス後の失業率低下に繋がります。
とはいえ、工場を移動させるのは企業にとって経営リスクを伴いますから、「果たしてこの金融緩和はしばらく続くのだろうか?すぐに終わったりしないだろうか?」となります。ここで上記の「工場はテレポーテーションできない」になります。
一部の企業は国内回帰に向かいますが、ある程度時間が経過すると「この金融緩和傾向は続きそうだ」と判断する企業が増えてきますので、2010年代後半に向けて本格的なインフレに寄っていきました。
その後は2020年でコロナ問題に直面し、特に人の移動や接触が制限され、となると「物流の停滞」に繋がります。ここでいったん経済は低迷。とはいえ、コロナがほぼ終わりを告げると、2023年以降の現状のインフレに話が結びつきます。
本当は「インフレ時における物価対策」について書きたかったですが、それを説明するために「デフレからインフレに向けた動き」について書きました。
~人気ブログランキングに参加しています~
良ければ応援クリックお願いします。