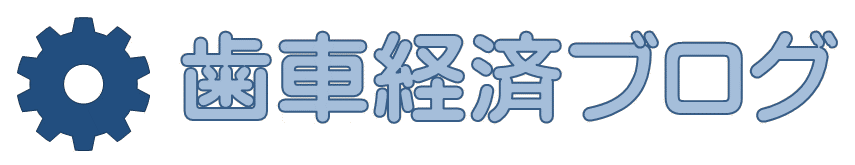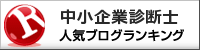人気ブログランキングに参加しています。
↓↓↓ まずはクリックお願いします。
デフレ対策とその後の動きについては前回のエントリで説明しました。デフレ期にはデフレ対策が必要で、具体的には財政出動と金融緩和。デフレの定義は物価の継続的な下落ですが、そこには貨幣価値や需要と供給のバランスがかかってきます。
デフレの時は概ね需要不足で、需要を底上げする政策が必要です。2010年代半ばぐらいにいったんはデフレを脱却できたものの、「しばらくはデフレ対策とほぼ同じ政策が必要」なのは、需要がまだ足りておらず、需要アップが必要だからです。
一応、需要と供給のバランスで行くと、デフレの時は「需要が足りない」わけですが、対応策として「供給を減らして需要とバランスさせる」という政策はよろしくなく、「需要をアップさせて供給に追いつかせる」という方向で考えるのが妥当になります。
これに対し、現状はインフレに振れつつあります。政府は特に「金利のある時代になった」と主張していますが、金利アップは「インフレ対策」になるためです。デフレの時は黒田バズーカはじめ、各種金融政策を打っていましたが、これをインフレになっても続けるわけにはいかない・・・というのは考えておいた方がいいです。
逆に現状ではデフレ脱却策と同じ政策を打つのはよろしくなく、「インフレ対策」を打つ必要があります。今度は供給よりも一部の市場で需要が上回ってきました。モノやサービスがよく売れると、事業者は値上げします。これが現在起こっている物価上昇になります。
需要が供給を上回ってきているわけです。このため「供給をいかに増やすか」を考えないといけません。「需要を下げてバランスさせる」は悪手になります。需要を下げる場合は「消費税増税」が好例になりますが、インフレ対策を目当てに「需要を減らす」はやはりよろしくありません。
物価高対策を考えると、「政府がその分を減税なり、助成金なりで補填する」というところを考えがちになりますが、これは「デフレ対策」に近く、政府の財政出動寄りになります。これをやると、インフレが加速し、状況は悪くなりやすいです。
そうなると、政府はあまり余計な事はやらず、「市場に任せる」あるいは「余計な規制があるのであれば、規制緩和して市場活性を促す。できれば民間にまかせる」という方がいいということになります。要は「供給を増やす政策」になります。
まあ、政治経済ブログや政治系のSNSを見ても、「供給を増やすことが重要だ」と主張している人は少ないようです。
~人気ブログランキングに参加しています~
良ければ応援クリックお願いします。